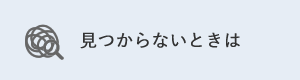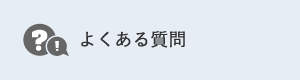国民年金保険料の免除、特例、猶予等
年金保険料が払えないからと、そのままにしていませんか?
未納のまま放っておくと、いざというときに年金が受けられなくなってしまします。
年金保険料を納付しない期間でも、「免除」と「未納」とでは大きく異なります。
次のいずれかに該当する方で、免除や猶予をご希望の方は申請してください。
法定免除
第1号被保険者(自営業、学生、無職の人など)が次のいずれかに該当したときは、届出により保険料が免除されます。
ただし、法定免除を受けた期間について老齢基礎年金の額を計算する場合、全額納付したときの2分の1になります(平成21年4月以降)。
対象者
- 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る)、国民年金・厚生年金・船員保険・共済年金から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付の受給権者になったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- ハンセン病療養所等、厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき
保険料免除制度
所得が少なく本人、世帯主及び配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
※ 学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
免除される額
- 全額免除
- 4分の1納付
- 2分の1納付
- 4分の3納付
対象期間 : 7月~翌年6月
原則として、年度ごとに申請手続きが必要です。
ただし、全額免除については申請時に「継続審査」を希望すると、翌年度から本人の申請が不要になる場合もあります。
その他
一部納付の方が納付すべき一部保険料を納めないと、一部免除が無効となり、未納と同じになりますのでご注意ください。
なお、平成21年4月以降、免除を受けた期間について老齢基礎年金の計算をする場合、それぞれ次のようになります。
| 免除の種別 | 支給割合 |
|---|---|
| 全額免除 | 2分の1 |
| 4分の1納付 | 8分の5 |
| 4分の2納付 | 8分の6 |
| 4分の3納付 | 8分の7 |
免除された期間は、10年以内であれば遡って保険料を納付できます。
将来、満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、納付されることをおすすめします。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予期間中に、万一、障害者になったり死亡した場合にも、一定の基準をみたしていれば、納付している場合と同様の「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」が支給されます。
ただし、猶予された期間については、老齢基礎年金の受給資格期間の計算には算入しますが、このままでは年金額の計算には算入されません。
納付猶予期間については10年以内であれば遡って納付することができます。
将来、満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、納付されることをおすすめします。
対象者 (平成28年7月以降)
以下の条件をすべて満たす人。
- 20歳から50歳未満の人
- 本人及び配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
対象期間 : 7月~翌年6月
原則として、年度ごとに申請手続きが必要です。
ただし、申請時に「継続審査」を希望すると、翌年度から本人の申請が不要になる場合もあります。
学生納付特例制度
20歳になれば、学生も国民年金に加入して保険料を納付しなければなりませんが、学生の方は所得が少ないことが一般的であることから、学生本人の所得が一定額以下の場合に、在学期間中の保険料を後払いできる制度です。
学生納付特例の承認を受けると、その期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受けとることができます。
ただし、猶予された期間については、老齢基礎年金の受給資格期間の計算には算入しますが、このままでは年金額の計算には算入されません。
納付猶予期間については10年以内であれば遡って納付することができます。
将来、満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、納付されることをおすすめします。
対象者
- 20歳以上で大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(学校教育法に規定されている修業年限が1年以上)等の在学生(夜間、定時制、通信制課程も含む)
- 学生本人の前年の所得が128万円以下の方(令和2年度以前の申請の場合は、118万円)
ただし、扶養親族、社会保険料控除等がある場合は、この限りではありません。
対象期間 : 4月~翌年3月
毎年、申請が必要です。 申請時には、年金手帳に加え学生証(写しでも可)又は在学証明書が必要です。
家族の方でも申請できますが、その際は必ず印鑑をご持参ください。
関連リンク (別ウィンドウで開きます)
- 日本年金機構ホームページ 法定免除<外部リンク>
- 日本年金機構ホームページ 保険料免除・猶予<外部リンク>
- 日本年金機構ホームページ 学生納付特例制度<外部リンク>
- 日本年金機構ホームページ 免除等申請可能期間<外部リンク>
- 日本年金機構ホームページ 追納<外部リンク>