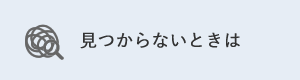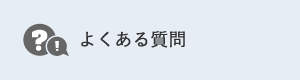畑の枯れ草焼きによる火災が多発しています。
1月に入り、畑の枯れ草焼きによる火災が多発しています。
畑などでの草焼き等は原則禁止されています。
これらの焼却は、大きな山火事の原因にもなります。
焼却しないように可能な限り可燃ゴミとして出しましょう。
みなさんの注意で火災を防ぎましょう。


野外焼却は原則、法律で禁じられています。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第16条の2(焼却禁止)

ただし、生活環境の保全のためや、宗教上又は農業上など、やむを得ない場合の焼却は、例外として扱われています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例・・・河川(ため池)管理に伐採した草木の焼却など)
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き、しめ縄焼却など)
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑、もみ殻、下枝焼却など) ※廃ビニール、廃プラスチック等の焼却は禁止
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(落ち葉焼却、キャンプファイヤーなど)
しかし、上記の焼却であっても、 推奨しているということではありません。焼却時に発生する煙やすすは、近所の方々の迷惑になります。時間帯や風向き、量に配慮が必要です。
やむなく、焼却を実施する場合に注意すること
(1)火入れ、たき火等又は煙火の消費は、火災予防上支障のないよう、消火準備その他必要な措置を講じて行ってください。
・いっぺんに何カ所も火をつけて、焼却をしない。
・刈った草等を集めず、周りに燃えやすいものがある場所で、焼却をしない。
・刈らず(立ち枯草)にそのまま焼却をしない。
・消火準備を何も用意しないで、焼却をしない。
・風が強い日や日が暮れて、焼却をしない。
(2)焼却規模に応じた人数で行い、絶えず警戒してください。
・一人で、広い範囲(予想以上に火が燃え広がりだしたときに対処できない範囲)の焼却をしない。
・焼却中に、その場を離れない。
(3)使用火の残火、マッチのすりかす、たばこの吸殻、煙火等すべての火気を完全に始末し、みだりに放置又は放棄しないでください。
・焼却の火が下火になったからといって、消火をせず、帰宅(その場を離れたり)しない。
・たばこを吸った後、すぐに吸殻をごみ箱に捨てた。
また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれがある(遠くにいる人から見て、火事と間違われるような)場合には、消防署への届出をお願いします。(※消防署への届出は、焼却行為等を許可するものではありません。)
■最後に、家庭からでるごみは、玉野市ごみ分別辞典に従って、分別をして出しましょう。