避難行動のポイント
梅雨の時期や台風接近時など、雨が多く降るときは、土砂災害や低い土地で浸水など災害が発生する恐れがあります。
台風が本市に接近するなどして、災害が発生する恐れがある場合や、市が避難情報を発令した場合には、適切な避難行動がとれるよう備えましょう。
(各災害の避難行動一覧)
▶「土砂災害」の場合
▶「地震」の場合
▶「津波」の場合
▶「高潮」の場合
▶「洪水」の場合
「土砂災害」の場合
自宅周辺の土砂災害警戒区域の指定状況や避難場所、避難経路などを事前に確認しましょう。
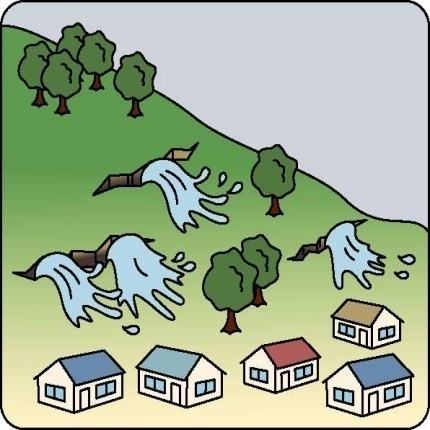
避難行動のポイント
- 住んでいる場所の土砂災害警戒区域の指定状況をハザードマップなどで確認する。
- 土砂災害警戒情報が発表された場合は、早めに避難を行う。
- 土砂災害の前兆現象に注意する。(主な前兆現象:地鳴り、山鳴り、小石が落ちてくる、土が腐った臭い、斜面から水が噴き出す等)
- ハザードマップを見て、土石流や崖崩れの起こる方向に対して横方向に避難(水平避難)する。
- 夜中や大雨の中など外へ避難を行うのが危険な時は、自宅2階以上の山の反対側の部屋や近くの堅固な建物の上階へ避難(垂直避難)する。
- 記録的短時間大雨情報が発表された場合は、早めに避難を行う。
その他
- 土砂災害警戒情報は、市ホームページ「土砂災害警戒情報が発表されたときの行動」をご覧ください。
- 土砂災害警戒区域を示したハザードマップは、市ホームページ「地域防災ハザードマップ」をご覧ください。
- 記録的短時間大雨情報とは、短時間で記録的な降雨を観測した場合に気象庁から発表される情報です。
玉野市の場合は、1時間に90mm以上の降雨があった場合に発表されます。また、本情報が発表された場合、玉野市防災メールマガジン、LINEで情報配信を行っています。
「地震」の場合
地震発生時の行動のポイントは、揺れを感じたら落ち着いて、まずは身の安全を確保することです。
大きな地震が起きたときは、電話等が通じにくくなったりするため、家族などとの連絡方法や集合場所、避難場所をあらかじめ決めておきましょう。
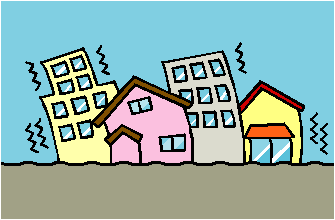
避難行動のポイント
- 緊急地震速報があった場合は、直ちに机の下へもぐるなど安全を確保する。
- 家の中でも柱に囲まれた場所(例えば、トイレ等)が比較的安全ですが、出入り口が1か所しかない部屋の場合、強い揺れにより家の構造がゆがんだ場合、扉が開かなくなるため注意する。
- 火の元の消火は、揺れがおさまってから落ち着いて行う。
- 屋外に避難する場合、塀や建物、電柱等は倒壊の恐れがあるため近付かない。
停電した場合は、通電した際に火災が起こる可能性があるため、ブレーカーを落として避難する。 - 土砂災害警戒区域の急傾斜地の崩壊に指定されているか所には近付かない。
- 自宅周辺の地震時待避場所を事前に調べておき、地震時や地震後に集合し、近所で安否確認や余震に備える。
- 大きな地震の場合は、津波が発生する可能性を考え、高台へ避難する。
その他
- 地震時待避場所は、市ホームページ「市が指定する災害時の避難所等のお知らせ」をご覧ください。
「津波」の場合
津波発生時の行動のポイントは、高い所への避難と情報収集です。地域の浸水予測や避難場所、避難経路などを事前に確認しましょう。

避難行動のポイント
- 強い揺れを感じたり、弱くても長い揺れが続いた場合には津波発生の可能性があるため、警報や注意報などが出ていなくても高台へ避難する。
- 大津波警報や津波警報が発表された場合は、ただちに近くの高台などの安全な場所へ避難する。
- 津波注意報の場合でも高い時には1m程度の津波が押し寄せることがあるため、避難が必要。
- 津波は繰り返し押し寄せ、第1波より第2、第3の波が高くなることがあるので、警報や注意報が解除されるまで高台への避難を継続し、海岸や河口付近には絶対に近づかない。
- 避難は、避難所ではなく、津波避難場所や高台などの広場へ。
- 建物内の上階への避難は危機迫り、ほかに手段がないとき以外は行わない。
その他
- 玉野市津波浸水想定を示したハザードマップは、市ホームページ「地域防災ハザードマップ」をご覧ください。
- 津波避難場所は、市ホームページ「災害時の避難場所について」をご覧ください。
「高潮」の場合
高潮による浸水に対する避難のポイントは、浸水区域外への避難と上階への避難です。高潮は台風襲来と合わせて発生することが多いため、潮位や台風進路など情報収集を行い、早め早めの行動が大切です。
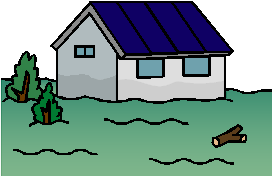
避難行動のポイント
- 新聞やインターネットなどで満潮、干潮の時間・高さを調べる。
- 台風進路や最接近時間がいつ頃なのかを調べる。
- 満潮の時間と台風最接近の時間が近い場合、土のうを積むなどして浸水防止の対策を行う。
- 時間に余裕があるうちに家財道具や貴重品など水に濡れると困るものは2階へ避難させる。
- 時間に余裕があるうちに避難の準備をする。(持ち出し品、避難先の確認、家族との連絡等)
- 避難所等へ避難する場合は、明るいうちに雨風が弱まったときに行う。
- 夜間や風・雨が強かったり、水位が上がり道路が冠水したりするような状況では、無理に避難所へ避難せず、自宅の2階以上に避難する。その際は、食料品や飲料水、貴重品等の必要なものも一緒に持って上がる。
- 高潮で浸水した場合、停電し、電気が使えなくなる恐れがあるため、懐中電灯など照明を準備する。
- 浸水している場所は、水が濁っており、がれき等の浮遊物、段差、ガラス片など危険が多く潜んでいるため、立ち入ったり、その中を通って避難したりするのは、大変危険なので行わない。
その他
- 平成16年度の台風16号による高潮で浸水した地域は、地域防災ハザードマップ津波版で示していますので、市ホームページ「地域防災ハザードマップ」をご覧ください。
- 新聞等に記載のある天文潮位について、120cm(1.2m)を差し引いたものが海抜高(T.P)になります。
平成16年16号台風での最高潮位は海抜高(T.P)で254cm(2.54m)です。 - 潮位情報は、気象庁ホームページ「潮汐・海面水のデータ<外部リンク>」を、台風情報は、気象庁ホームページ「台風情報<外部リンク>」をご覧ください。
「洪水」の場合
洪水による浸水に対する避難のポイントは、高潮と同じく浸水区域外への避難と上階への避難です。台風の大雨や短時間の豪雨によって発生することが多く、情報収集を行い、早め早めの行動が大切です。
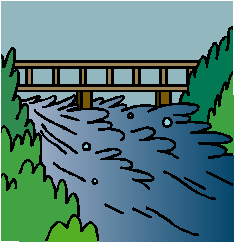
避難行動のポイント
- 天気予報や雨雲の動きをテレビやインターネットで入手する。
- 河川上流で大雨が降った場合、下流域では急激に水位が変化するため注意する。
- 水位の増した河川へ近づくことは危険なので、水位を確かめに行くなどせず、河川管理者から提供される情報の入手に努める。
- 記録的短時間大雨情報が発表された場合は、浸水の恐れがあるため避難を行ったり、家財道具の移動を行う。
- 時間に余裕があれば、家財道具や貴重品など水に濡れると困るものは2階へ避難させる。
- 時間に余裕があれば、避難の準備をする。(持ち出し品、避難先の確認、家族との連絡等)
- 大きな河川が増水し、堤防が決壊する恐れがあるときは、直ちに避難所等へ避難を行う。
- 用水路の溢水等による浸水の恐れがある場合に避難するときは、明るいうち、雨の勢いが落ち着いたときに行う。
- 夜間や雨が強まり、用水路等が超水しそうな状況で外へ避難することが危険な場合は、無理に避難所へ避難せず、自宅2階以上に避難する。その際には、食料品や飲料水、貴重品等の必要なものも一緒に持って上がる。
- 浸水した場合、停電し、電気が使えなくなる恐れがあるため、懐中電灯など照明を準備する。
- 浸水している場所は、水が濁っており、がれき等の浮遊物、段差、ガラス片など危険が多く潜んでいるため、立ち入ったり、無理にその中を通って避難したりするのは、大変危険なので行わない。
その他
- 市内で平成以降に発生した内水氾濫の実績を示したマップは、市ホームページ「内水ハザードマップ」をご覧ください。
- 県内の各主要河川の推移の状況は、県ホームページ「おかやま防災ポータル<外部リンク>」をご覧ください。
- 児島湖の水位情報は、県ホームページ「児島湖水位情報<外部リンク>」をご覧ください。
- 雨雲の動きは、気象庁ホームページ「高解像度降雨ナウキャスト<外部リンク>」をご覧ください。
- 記録的短時間大雨情報とは、短時間で記録的な降雨を観測した場合に気象庁から発表される情報です。
玉野市の場合は、1時間に90mm以上の降雨の場合発表されます。また、本情報が発表された場合、玉野市防災メールマガジン、LINEで情報配信を行っています。
自然災害は、思いもよらない場所で発生したり、想像や想定を超える規模の被害をもたらす可能性がありますので、ハザードマップで浸水区域や危険区域に入っていない、過去に何も災害が起こったことがないからといって安心せず、大雨が降り続いたり、局地的豪雨や大きな地震などがあった際には十分注意してください。
